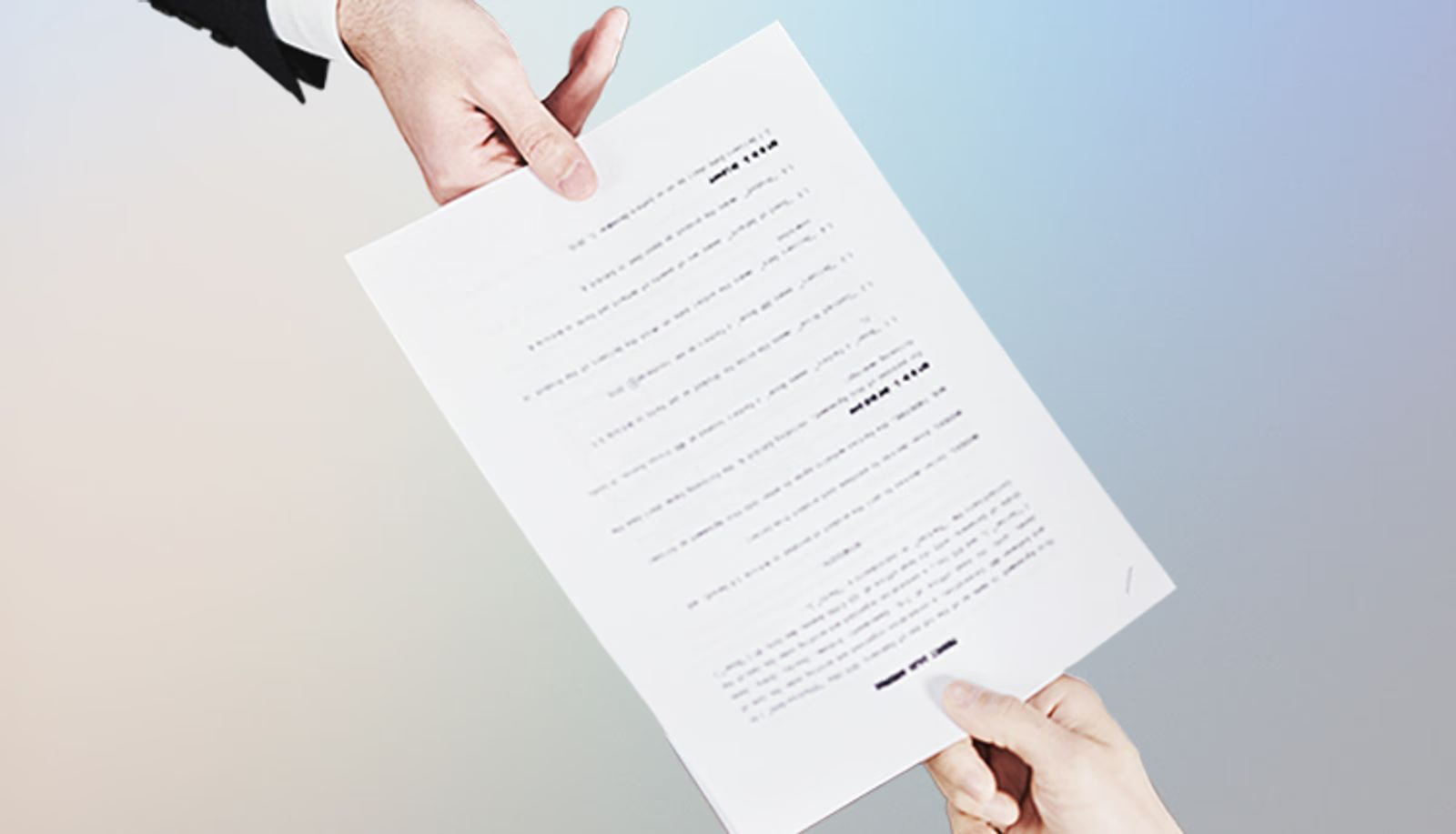リーガルチェックの意味は「契約書を法的な視点で検証・チェックすること」
リーガルチェックとは「契約書を法的な視点で検証・チェックすること」です。ビジネスの観点だけでなく、内容が法的に問題ないかも併せて確認します。
ビジネス間取引で契約書に法的な問題があると、代金の不払いやクレームなどのトラブルに発展するケースも珍しくありません。法律違反に加え、契約書による合意の内容が明確かなど、取引に関する事項を法的な視点からチェックするのもリーガルチェックの目的です。
チェック対象となる契約書は大きく分けて以下の2通りです。
- 自社で作成した契約書
- 他社から受領した契約書
自社で作成した契約書のチェック内容
自社で作成した契約書は、主に下記の点をリーガルチェックします。
- 関係する事業部に対し文言の修正を提案すること
- 契約書にコメント等で記されている質問に答えること
契約書は作成にあたり、自社製品・サービスには専門家が監修・作成した契約書のひな型を用意していることがほとんどです。ひな型に不十分な点があれば、事業部がビジネスの実態に合わせて加筆・修正を施します。
事業部が加筆修正した契約書に対して、法務部や弁護士は、下記の点がどうかを精査します。
- 修正内容がビジネスの実態に沿っているか
- 法律上の強行規定に違反していないか
- 自社のリスクは許容範囲内に抑えられているか
そして不備があれば、修正や加筆の提案を事業部に対して行います。なお、契約書に適用される法律は、企業の資本金や従業員数によって変わることがある点に注意が必要です。リーガルチェックの効果が薄くなってしまうので、弁護士に依頼する際は、企業情報をできる限り正確に共有しましょう。
他社から受領した契約書のチェック内容
他社で作成・受領した契約書は、主に下記の点をリーガルチェックします。
- 予定している取引の実態がきちんと反映されているか
- 自社にとって許容できないような不利な条項がないか
- 法令違反や無効となる原因など、法律上問題のある条項がないか
不明点があれば相手方に説明を求めます。
加えて、文言に対案を提示し、相手方に修正を促すことがリーガルチェックの内容になります。
契約の基本についてさらに詳しく知りたい方は、以下の無料ダウンロード資料もご利用ください。
「契約とは何で、契約書にはどのような記載をすればいいのかよくくわからない」というお悩みをお持ちの方におすすめの資料を無料で配布しています。
「【新任~若手法務向け】契約の基本がわかるハンドブック」をダウンロードする
関連記事:契約書レビュー業務の流れを細かく解説!
リーガルチェックのメリットと重要性
上記でご紹介した内容から、企業のリスク管理には欠かせないリーガルチェックですが、必要であると同時に下記のメリットがあります。
- 取引の実態に即した契約書が作成できる
- 両当事者間の認識の相違を事前に把握し、トラブルを回避できる
- 自社にとって不利な条項や抜け漏れを事前に発見・修正提案できる
- 契約が無効になることを防げる
- 法律に違反するような契約内容でないか確認できる
- 企業の信用度の低下を防げる
それぞれについて、もう少し詳しく見てみましょう。
メリット①取引の実態に即した契約書が作成できる
リーガルチェックを受けることで、取引の実態に即した契約書が作成でき、リスクを未然に防止できます。
ビジネスは流動的で常に変化をしているため、ひな型の文言だけでは取引の実態に合わせた契約書が作成できないことがあります。支払の条件なども、標準的な文言ではなく、取引にあわせてアレンジすることが妥当な場合もあるでしょう。
取引の実態にあわせた契約書を作成しないと、取引のフローが不明確になる・取引の中で生じるトラブルに対応できないなどのリスクが生じる可能性が高くなってしまいます。
メリット②両当事者間の認識の相違を事前に把握し、トラブルを回避できる
リーガルチェックでは、不明点を法務部や弁護士に質問したり、相手方に確認したりすることにより、曖昧な契約内容を明確化できます。契約書に記載される内容は、一言一句が業務上または法的な意味を持つため、曖昧な表記があると誤解を招くケースも珍しくありません。
また、自社にて契約書を作成する場合、自社の利益を追求し過ぎた内容だと相手方が不信感を抱き、信頼関係が崩れてしまいかねません。
リーガルチェックを行うことで、曖昧な言葉や用語の間違いのチェックができ、当事者間の理解違い・認識違いを防げるでしょう。理解を合わせるためのコミュニケーションが生まれるので、紛争に発展するリスクを事前に避けることにも期待できます。
契約書をめぐって発生しやすいトラブルや対策は下記の記事で解説しているので、ぜひ合わせて参考にしてください。
関連記事
契約書をめぐるトラブルを防止するには?必要な対策・管理方法を解説
メリット③自社にとって不利な条項や抜け漏れを事前に発見・修正提案できる
リーガルチェックは、自社にとって不利な条項を見つけられる点もメリットです。
相手方から提示される契約書の多くには、相手方に有利な条件が、盛り込まれることがあります。自社にとって不利な条項については修正案を合理的な理由とともに提示し、契約交渉をサポートするのもリーガルチェックの重要な役割です。
メリット④契約が無効になることを防げる
リーガルチェックを行い、違法・無効な規定を発見・修正することで、契約無効によるトラブルのリスクを回避できるメリットがあります。
契約には法的な効力がありますが、公序良俗違反や、消費者契約法などの強行法規違反により、全部または一部が無効になってしまうケースがあります。
契約が無効になってしまうと、予期せぬ結果を招き、相手方とのトラブルも避けられないため、リーガルチェックで事前に防ぐのがおすすめです。
メリット⑤法律に違反するような契約内容でないか確認できる
契約内容が法律違反であることに気づかないまま契約を締結してしまうケースがあります。
法律違反は契約が無効となるだけでなく、行政処分・行政指導の対象となることがあります。場合によっては、営業停止や営業許可取り消しなどの重い処分が下されかねません。リーガルチェックを実施し、契約内容に法律違反がないか事前にチェックしておくことが大切です。
メリット⑥企業信用度の低下を防げる
法律違反や無効となる契約をしてしまうと、企業に対する社会的な信用を失ってしまいます。法律違反の契約により、社会的な信用を失ったことで、倒産に追い込まれた企業も少なくありません。リーガルチェックを実施すると、適切な内容で契約を締結でき、企業の信頼性の低下を防げます。
メリット⑦トラブルに発展した際、想定外の不利益が生じるリスクを減
らせる
万が一トラブルに発展した際に、想定外の不利益が生じるリスクを軽減できることも、リーガルチェックが必要な理由です。契約書には、トラブルが発生した際の対処についても記載されていることがあります。取引に関する条項はしっかりとチェックされる傾向にありますが、トラブルが発生したときの条項については、見落とされることも少なくありません。
内容によっては、トラブル時に多大な損失を被る恐れがあるため、契約書はトラブルに関する条項までしっかりとチェックしましょう。
リーガルチェックの流れ|社内のみで実施する場合
まずは、社内でリーガルチェックを実施する場合の手順を紹介します。チェックの精度を高めるには、適切な手順で実施するのが重要です。社内で実施する場合は、以下の流れで行います。
- リーガルチェックの依頼を受け付ける
- 契約内容を把握する
- 契約書ドラフト内の修正点を洗い出す
- 担当部署へチェック結果を返す
- 契約を締結する
なお、自社の法務部門だけでチェックを完結させるケースもありますが、自社のみでの対応が難しいときは、弁護士への依頼を検討しましょう。特に新しいタイプの契約や、相手方がドラフトを作成した契約については、外部の弁護士にもチェックを依頼するのが安心です。
①リーガルチェックの依頼を受け付ける
まずは、営業部門などの担当部署から契約書のリーガルチェックを受け付けます。
受け付けた案件は、業務状況や過去の取り扱い案件などを考慮して、適任と思われる法務担当者に割り当てましょう。割り当て作業を効率化するため、リーガルチェックの受付窓口は一本化するのがおすすめです。
リーガルチェックを受け付ける際には、担当部署から案件の概要をヒアリングする必要があります。
具体的には、取引の目的(なぜこの取引を行うのか)と背景(取引に至った経緯)をヒアリングしておきましょう。実際に契約書のリーガルチェックを行うにあたり、取引の目的・背景によって付すべき修正コメントの内容が変わってくるためです。
効率的かつ漏れなくヒアリングを行うためには、契約審査依頼用の書式やデータベースを作成し、必要な情報を記入してもらうなどの対策を講じましょう。
リーガルチェックの適切な手法は、会社の状況によって異なるため、自社にとって最適なフローを模索することが必要です。
②契約内容を把握する
法務担当者がリーガルチェックを行うに際には、はじめに契約内容を把握する必要があります。
漫然と読み進めるのではなく、要点を捉えて順序よく確認し、契約の全体像を理解することが大切です。具体的には、以下のような手順を経るのがよいでしょう。
- 契約に基づき予定される取引の内容を確認する
(例)
プログラムの制作業務を委託する内容の業務委託契約である。
- 取引の要素が記載されている条項を確認する
(例)
委託業務の内容を確認する。さらに具体的な発注・受注について、その方法や納期、報酬の決定方法・支払方法・支払期限などを確認する。
- 当事者の権利義務が記載されている条項を確認する
(例)
受託者の義務に関する条項を確認する。
- 一般条項を確認する
(例)
契約期間、損害賠償、秘密保持義務、反社会的勢力の排除、合意管轄などに関する条項を確認する。
なお、過去に締結した関連契約が存在する場合には、今回の契約との関係性を確認するため、関連契約にも早めに目を通しておきましょう。
③契約書ドラフト内の修正点を洗い出す
契約書の全体像が把握できた段階で、修正コメントを付すべきポイントを洗い出します。修正すべき主なポイントは、以下のとおりです。
- 自社にとって明らかに不利益な条項
法律上の任意規定や実務のスタンダードに照らして、自社にとって明らかに不利益と思われる条項については、修正を求める必要があります。
- 自社のひな形と異なる内容・水準の条項
オペレーションの統一を図るため、同種取引に関する自社のひな形と比較して、異なる内容・水準の条項は修正することが望ましいです。
- 法令違反の条項
法律上の強行規定に違反する条項は無効となるため、修正が必要になります。また、業法によって規定が義務付けられている事項が漏れている場合や、不正確なときに、追記・修正を行わなければなりません。適用される法律は会社の状況や業務によって異なるので、チェックの精度を高めるためにも、必要な情報は事前にまとめておきましょう。
- 誤記・表記ゆれなどの形式的不備
誤字・脱字、表記ゆれ、条ズレ、段落の乱れなどの形式的不備は、当事者のうち気づいた側が随時修正します。
相手方の反発が予想される修正については、その理由を丁寧に記載することが大切です。修正理由が合理的なものであれば、相手方も受け入れる可能性が高まります。
自社のみでのチェックが不安なときは、社外の弁護士にもリーガルチェックを依頼すると安心です。
④担当部署へチェック結果を返す
ドラフトへの修正コメントが完了したら、担当部署へリーガルチェックの結果を返答します。
営業担当者などは、必ずしも法的な知識を有していないケースがあります。相手方との交渉を円滑に進めるためにも、なぜ修正が必要なのかについて、法的素養のない人でも正しく理解できる言葉で補足説明を行いましょう。
相手方との契約交渉は、法務部門ではなく担当部署が行うのが通常です。そのため、どのような言葉で相手方に修正を依頼するべきかについても、法務担当者からできる限り提案するのが親切でしょう。
実際のリーガルチェックでは、担当部署とコミュニケーションを取りながら、相手方に返送するファイルを完成させていくのが一般的です。
相手方向けの修正コメントと担当部署向けの確認コメントを使い分けると、やり取りがスムーズに進みます。トラブルを避けるためにも、相手方へ契約書ファイルを返送する前には、法務部門と担当部署の間で認識の相違を解消しておきましょう。
⑤契約を締結する
相手方との間で何度かコメントをやり取りした後、契約書全体について合意に至った段階で、最終版の契約書ファイルを作成します。
最終版の段階では、誤記・表記ゆれなど形式的不備の修正を含めて、完全な状態の契約書ファイルを作成する必要があります。法務部門・担当部署のそれぞれで慎重にチェックを行い、不備が残っていないかどうかを慎重に確認しましょう。
また、交渉段階のファイルと混同しないように、ファイル名などを工夫して適切にバージョン管理を行うことも大切です。
契約の締結では、書面を作成して署名捺印(または記名押印)を行う方法のほか、電子契約として電子署名を付す方法がよく用いられます。どのような方法で契約を締結するかについては、営業担当者を通じて、相手方との間で事前に調整しておきましょう。
締結後の契約書は、適切な方法によって保管・保存する必要があります。とくに法律で保存期間が定められた契約書は、必ず定められた期間、適切な手法で保存しなければなりません。書面・電子契約のいずれであっても、アクセスできる役員・従業員の範囲を最小限に絞り、情報セキュリティの確保を図りましょう。
リーガルチェックの流れ|弁護士に依頼する場合
つづいてリーガルチェックを自社のみでなく、弁護士にも依頼するときの手順です。弁護士に業務を依頼するときは、以下のような流れで進めます。
- チェックしてもらいたい契約書を準備する
- 自社の会社情報や取引に関する情報をまとめて提出
- 弁護士からのフィードバックを受ける
- 契約書の修正と取引先との交渉をおこなう
- 双方の合意のもと契約締結
①チェックしてもらいたい契約書を準備する
まずは自社で作成した契約書、または取引先から受け付けた契約書を準備します。このとき、自社でも一度しっかりと確認することが大切です。弁護士に依頼するからといって、確認しないまま丸投げしてしまうと、のちにトラブルに発展する場合があります。契約書の内容については、自社でもきちんと把握しておきましょう。
②自社の会社情報や取引に関する情報をまとめて提出
会社や取引の状況によっては、適用される内容が異なる法律もあるため、弁護士には自社の情報や取引に関する情報を共有する必要があります。正確な情報を提出しないと適切に判断できないため、必要な部分は正確に伝えましょう。
また、顧問弁護士を常用しており、自社の内情に理解があったとしても、変更点や初めて取引するクライアントなどのときは、情報を提供することが大切です。
なお、取引に関して要望や希望がある場合は、あらかじめ相談しておきましょう。要望や希望を考慮しつつ、法的な観点からチェックをおこなってくれます。契約書と情報を提出したら、リーガルチェックの事前準備は完了し、弁護士が確認を進めます。
③弁護士からのフィードバックを受ける
チェックが済んだら、弁護士によるフィードバックです。契約書をチェックし、クライアントの要望を考慮しつつ、問題点や改善点を指摘してくれます。ただし、弁護士は自社の業界に必ずしも精通しているとは限りません。
④契約書の修正と取引先との交渉をおこなう
修正内容がまとまったら修正をおこないます。自社が契約書を作成したときは、修正内容を反映させたうえ、営業担当者を通じて取引先と交渉をおこないましょう。契約書を取引先が作成した場合は、営業担当者に修正内容を共有し、取引先に内容の変更をお願いします。
⑤双方の合意のもと契約締結
双方の合意が得らえたら契約を締結しますが、締結する前に弁護士へ最終調整の確認を依頼するのがおすすめです。弁護士による最終確認の際に問題がなければ、契約書を締結しましょう。
リーガルチェックで抑えておくべきポイントと注意点6選
リーガルチェックには法務担当者や弁護士があたります。法務部が設置された企業では、まず法務担当者によるリーガルチェックが行われるのが一般的です。法務部によるチェックの際、法的に難しく判断がつきにくいポイントがあれば、社外弁護士の意見を求めるという手順でチェックを進めていきます。
法務担当者は、リーガルチェックをする際、次のような要点をおさえておくことが必要です。
- 契約書内の用語などについて不明点を確認する
- 関係する法令や判例を調査する
- 自社にとって不利な条項や抜け漏れがないかをチェックする
- 関連する契約書との整合性をチェックする
- トラブルを想定した内容にする
- 自社の目的や取引の実態に即した内容かチェックする
「どのように進めるのか」、「なぜこれらがポイントになるのか」については、以下で詳しく見ていきましょう。
注意点①契約書内の用語などについて不明点を確認する
法務担当者がリーガルチェックを行う場合は、曖昧な専門用語・業界用語はそのままにせず、分かりやすい言葉への変換が必要です。
契約書には業界用語や専門用語をはじめ、日常では使用しない用語が使われている場合があります。
しかし、契約書の言葉が正確に伝わらないと、当事者間の合意の内容がずれてしまいかねません。契約の対象サービスや製品のような重要な要素にも認識の違いが生じてしまうことがあるでしょう。こうしたずれをそのままにすると、代金の支払拒否、製品の引き渡し拒否、ひいては訴訟などのトラブルに発展する確率が高くなります。
難しい業界用語などは「なんとなくわかったような気がする」でつい進めてしまいがちですが、リスク管理のためには曖昧な対応は禁物です。
注意点②関係する法令や判例を調査する
関係する法令や判例の調査もリーガルチェックに欠かせません。
契約条項に記載されていない事項については、法令や判例に従った処理が行われます。そのため、取引に適用され得る法令・判例のルールを理解しておくことは非常に重要です。また、強行法規違反の契約条項がある場合には修正が必要ですので、その点でも法令・判例のリサーチは大きな意味を持ちます。
自社で契約書を作成する場合は、ひな型を作るときに調査を実施することが多いですが、相手方から受領した契約書に関しては、法律違反がないかチェックが必要です。
なお、法律は定期的に改正されることがあります。法律が改正されると、契約書の内容も変更が必要な場合が出てくるため、自社に関連する法律や法令は定期的にチェックしておきましょう。
注意点③自社にとって不利な条項や抜け漏れがないかをチェックする
基本的に相手方であるベンダーや、専門業者などから提示される契約書は、相手方に有利な条項が多く含まれています。不合理な条項がある場合は、必要に応じて修正・削除し、フェアなとなるよう交渉しなければなりません。
また、条項に不足・抜け漏れがないかチェックし、取引条件の中で明確に記載すべきであるのに記載していない条項がないかの確認も必要です。法令や判例に照らして記載すべき条件などがあるときは、必要に応じて加筆します。
注意点④関連する契約書との整合性をチェックする
関連する契約書と矛盾した内容の契約書を締結したり、過去の契約変更などを見落としたまま契約書を締結したりすると、業務に支障が生じます。業種によっては法令違反のリスクが生じるでしょう。
新規に契約書を締結する際には、過去に締結した関連契約との整合性をチェックしなければなりません。関連契約すべてに目を通しながら、矛盾や法律違反が生じていないかリーガルチェックを行うことが大切です。
注意点⑤トラブルを想定した内容にする
リーガルチェックは想定されるトラブルを未然に防止できるかという観点から行う必要があります。
損害賠償に関する条項・解除ないし途中解約に関する条項のほか、機密保持義務の範囲なども、トラブル防止の観点から熟慮すべき事柄です。
また、実際にトラブルがあった場合の処理手順を、明確な形で契約書に書き込んでおくことも重要になります。
機密保持契約・売買契約・ライセンス契約など、契約内容に応じて、トラブルの予防・対処の観点から十分な内容かどうかをチェックしましょう。
注意点⑥自社の目的や取引の実態に即した内容かチェックする
契約書に取引の目的・実態が適切に反映されているかを確認するため、関係各所への十分なヒアリングを行う必要があります。取引の目的・実態が契約書内容が乖離していると、取引のフローに不明確な部分が生じるためです。トラブルが発生した際には、適切に対処できないといった問題が生じる可能性もあります。
契約内容と取引の目的・実態との整合性について、少しでも疑問に思う点があれば、所管部に十分なヒアリングを行って解決しましょう。
リーガルチェックに関するよくある質問
ここでは、リーガルチェックに関するよくある質問をまとめました。法務部でチェックに取り組む前には一度チームないで確認しておくとよいでしょう。
リーガルチェックはどこに依頼するのがベストですか?
リーガルチェックを担当するのは、自社の法務部門もしくは、弁護士をはじめとする法律の専門家です。ベストな依頼先は、企業の目的や状況によって異なるため、一概にはいえません。
たとえば弁護士への依頼は、専門的にチェックしてくれるのがメリットです。法律のプロが様々な角度からチェック・提案をおこなってくれるため、チェックの精度を重視するときは、弁護士への依頼がベストといえます。コスト重視で考えるときは、自社の法務部門によるチェックが有力候補です。自社の目的や優先事項をふまえ、適した手法を選択しましょう。
弁護士にリーガルチェックを依頼する際の費用はどのくらいですか?
弁護士にリーガルチェックを依頼する場合は、要望や依頼内容によって費用が変動し、5~15万円ほどが相場です。継続的なアドバイスを求める場合は、さらに追加費用が発生する場合があります。
費用は法律事務所の規模によっても異なるため、リーガルチェックを弁護士に依頼する際は、あらかじめ依頼する範囲を社内で決めておきましょう。
リーガルチェックの業務効率化を図る方法はありますか?
リーガルチェックの業務効率化には、弁護士への依頼のほか、契約書レビューサービスをはじめとするITの導入が有効です。
たとえば契約書レビューサービスでは、契約書を読みこませるだけで、AIが自動的にリーガルチェックを実施してくれます。人間がおこなっていた業務の削減が図れるため、業務効率化に期待できます。
契約書レビューサービスとは
契約書レビューサービスとは、AIが自動的にリーガルチェックを実施するサービスです。契約書をシステムにアップロードすると、AIが契約書内のリスクを洗い出し、改善案などを提案してくれます。各サービスには、様々な機能が搭載されており、種類も豊富です。
契約書レビューサービスの主な機能
たとえば、自動レビュー機能は、契約書のアップロード後にAIが自動でレビューしてくれる機能です。サービスによっては、リスク度合いの色別表示や、実際に起きた事例を紹介するものなどもあります。
また、修正に機能では例文を提示してくれるものもあり、修正の参考にできて便利です。加えて管理機能で契約書のデータベース化も図れるため、過去の契約書をすぐに確認できます。
サービスによって搭載される機能は異なるため、自社に合った機能のサービスを選びましょう。
契約書レビューサービスを利用するメリット
契約書レビューサービスの利用には、以下のようなメリットがあります。
- 契約書チェック業務の効率化を図れる
- チェック業務の精度向上につながる
- 自社にリーガルチェックのノウハウを蓄積できる
まずは、契約書チェック業務の効率化を図れることです。人間がおこなっていた業務をAIに任せられるため、チェック業務にかかる時間と労力を軽減できます。また、人間だと「チェック漏れ」「見落とし」など、ヒューマンエラーはどうしても発生するものです。サービスを活用することで、見落としやチェック漏れを防止できます。
そのほか、自社にリーガルチェックのノウハウを蓄積できる点もメリットです。業務の属人化も防げるため、法務部門の適切な体制構築にもつながります。
契約書レビューサービスを選ぶときのポイント
契約書レビューサービスを選ぶときは、以下のポイントをおさえておきましょう。
- 自社のチェック水準を満たしているか
- 自社がレビューをしたい契約書の種類に対応しているか
- 多言語に対応しているか
- 自社が利用したい機能が搭載されているか
- 予算に合うか
契約書レビューサービスは、自社のチェック水準を満たしたものを選ぶことが大事です。企業によっては、独自のチェックルールを設けていることもあるでしょう。チェック水準を満たしていないサービスを選んでも、十分に確認できません。サービスの中には、独自の修正方針や確認項目などを登録できるものもあるため、独自の水準を定めているときは、これらの機能があるサービスを選びましょう。
また、レビューが可能な契約書の種類も確認しておきたいポイントです。対応できる種類が豊富であれば、新規事業などで契約書の種類が増えても対応しやすく、ほかのサービスを探す手間が省けます。
なお、無料トライアルを利用できるときは、使用感を確かめたうえで判断するのがおすすめです。使いやすいサービスをチョイスすることで、担当者がスムーズに業務を進めやすくなり、更なる業務効率化を図れます。
リーガルチェックする契約書の例・種類
リーガルチェックを行う対象となる代表的な契約書の例は次のとおりです。
- 秘密保持契約書
- 売買契約書
- 業務委託契約書
- 基本契約書
- ライセンス契約書
秘密保持契約書
一定の情報を第三者に対して開示しないこと、情報の利用目的を定め目的外使用を禁止することや、情報の取り扱いのルールを定める内容を持つ契約書です。
売買契約書
不動産・動産に関する売買取引の条件を売買契約書で定めます。売買の対象物・価格・危険負担や保険・引き渡し方法など、売買にまつわる詳細の条件を定めます。
契約の内容が不十分であると取引が実行できなくなるので、これらの条件に抜けや漏れがないか、しっかりチェックをする必要がある契約書です。
業務委託契約書
業務委託契約書は、サービスの提供を目的とする契約書です。ソフトウェアの開発委託・コンサルティングの委託・販売委託・人材紹介の委託・研修委託などの契約書の性質は基本的に業務委託契約書です。
サービスは多様なため、「サービスの性質に応じた条項であるか」、「業務委託で生じる著作権の帰属」など、重要な内容が明確であるかがポイントになります。
基本契約書
反復して生じる取引の基本条件を定めるのが基本契約書です。基本契約書は契約の基本的なルールを定めたもので、基本契約書があると、個別の取引は簡略な個別契約書により進められます。個別契約書は取引や現場でのルールをより具体的に定めたもので、基本契約書の内容に基づいてするのが一般的です。
基本契約書は、その後の取引条件を決める性質の契約書ですので、ひな型の作成時や相手方から受け取る際は、入念にチェックを行う必要があります。
なお、個別契約書のレビューにおいては、個別契約書が基本契約書の内容に優先するのか、基本契約書の内容通りかの点もレビューのポイントとなります。
ライセンス契約書
ライセンス契約書は、ソフトウェアの著作権・特許権などを持つライセンサーから、ライセンシーに利用する権利を設定する契約書です。許容される利用内容・利用形態の理解、第三者から権利侵害の主張があった場合の取り決め事項などが、レビューのポイントになります。
ソフトウェアライセンス契約書は、主に書面によるものと、シュリンクラップという形式でソフトウェアの利用の際にPC等の画面上で同意するものの2種類です(エンドユーザーライセンス=EULAと呼ばれます)。そこでこの場合、書面によるライセンス契約と、エンドユーザーライセンスの関係も重要なポイントとなります。
まとめ:リーガルチェックのメリット・重要性とやり方
リーガルチェックで確認する点は主に下記です。
- 契約書内の用語などについて不明点を確認する
- 関係する法令や判例を調査する
- 自社にとって不利な条項や抜け漏れがないかをチェックする
- 関連する契約書との整合性をチェックする
- トラブルを想定した内容にする
- 自社の目的や取引の実態に即した内容かチェックする
リーガルチェックを実施すると、契約書による合意の内容が明確か、などをはじめ、ビジネスに関する事項を法的にチェックできます。
法務をシームレスに支援する次世代リーガルテック「LegalOn Cloud」
「LegalOn Cloud」は、法務業務をシームレスに支援する次世代リーガルテックです。契約審査から締結後の契約管理、法務相談案件の管理、法令リサーチ、法改正対応まで、あらゆる法務業務を最先端のAIを搭載したLegalOn Cloudがカバーします。日々の業務の中で生まれる自社の法務ナレッジ。LegalOn Cloudなら自然に集約、AIが自動で整理し適切なタイミングでレコメンド。ナレッジマネジメントの未来の形を実現します。
【新任~若手法務の方へ】
そもそも契約とは何か、なぜ契約書を作成するのか、正しく答えられますか?
以下の無料資料をダウンロードして、契約の基本を網羅的に理解しましょう。
「【新任~若手法務向け】契約の基本がわかるハンドブック」をダウンロードする
<この記事を書いた人>
Nobisiro編集部
AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供するLegalOn Technologiesが運営する、法務の可能性を広げるメディア「Nobisiro」編集部。の法務担当者の日々の業務に役立つ情報を発信しています。