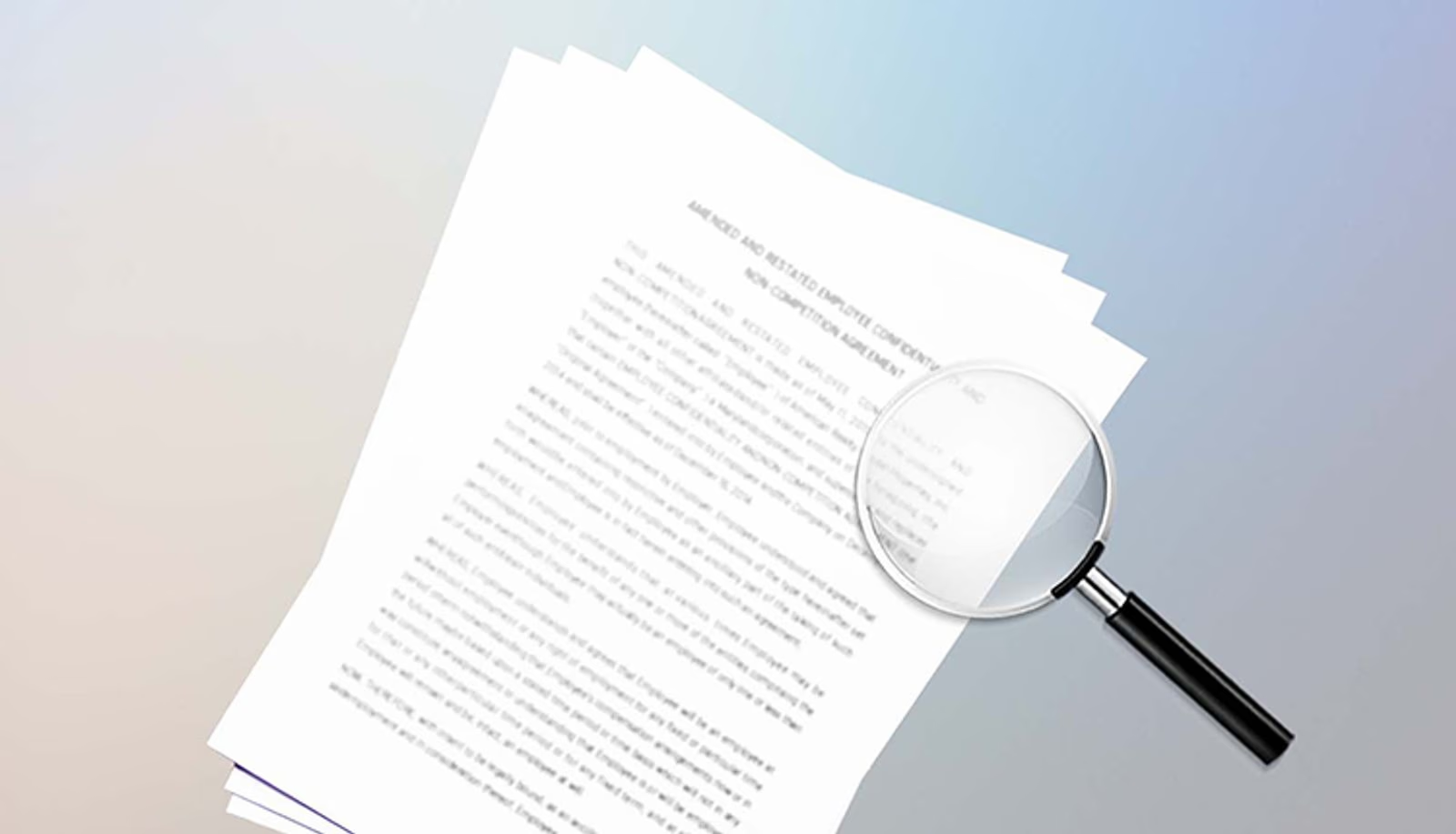契約書レビューとは
契約書レビューとは「契約書による合意の内容が明確か、予期しない隠れたリスクが書面から生じないかを法的な視点からチェックする業務」です。
契約書に不備があると、思わぬトラブルに発展する可能性があるため、契約書レビューは契約書業務の中でも最も重要な工程です。
レビュー対象となる契約書は大きく分けて以下の2種類です。
- 自社で作成した契約書
- 他社から受領した契約書
自社で契約書を作成する場合、事業部がビジネスの実態に合わせて加筆・修正をひな型に施します。
そして法務部や弁護士が、修正内容がビジネスの実態に沿っているか、法律上の強行規定に違反していないかなどを精査し、修正や加筆を事業部に提案します。
他社で作成・受領した契約書には、不明点は相手方に説明を求めて、予定している取引の実態が反映されているか、自社にとって許容できないような不利な条項がないかなどを確認します。
また、文言に対案を提示して相手方に修正を促すことがレビューの内容です。
関連記事
相手方契約書を受け取った後の契約書レビュー業務のやり方・流れ
契約書には、自社で作成した契約書と取引の相手方が作成した契約書の2種類あります。
今回は、取引の相手方が作成した契約書を受け取った場合に、契約締結に向けてどのように契約書をレビューしていけばよいかの流れを解説します。
- 契約内容を把握する
- リスクを抽出する
- 修正案を作成する
- 修正案を確認する
それぞれ詳しく解説します。
関連記事
契約書のリーガルチェックとは?意味やメリット、実施する手順を徹底解説【2024年最新版】
STEP1.契約内容を把握する
取引において、自社作成の契約書を使用する場合は、契約書にどのようなことが規定されているのか既に把握できている状態のため、 相手方が修正してきた箇所のみ検討すれば良いです。
しかし相手方が作成した契約書を使用する場合は、 その契約書にどのようなことが規定されているのかを把握することからスタートします。
- 何についての契約かを把握する
- 契約の目的を明確にする
- 契約期間や契約金額を確認する
何についての契約かを把握する
まず、具体的にどのような取引を行おうとしているのか、そもそも契約書を作成する必要があるのか、など、契約を締結する目的を把握します。
企業活動においては、以下のような様々な取引が行われます。
- 新製品や新システムの共同開発を検討するために、相手方と情報交換したい
- 社員が増えたため、オフィスを借りたい
- 自社が受注した開発の一部を外注したい
- 作業効率化のためにツールを導入したい
取引の内容によっては、契約書への記載が法律上要求される事項などがある場合もありますので、 その取引に必要な取り決めを契約に過不足なく落とし込むために、取引の内容をきちんと把握しましょう。
契約の目的を明確にする
次に、契約を締結をすることで自社が目指す契約の目的(契約で自社が得られる効果や価値)を明確にします。
例えば、「新製品や新システムの共同開発を検討するために、相手方と情報交換したい」場合、相手方に自社の情報を開示することがあります。しかし、 開示した相手方に自社の秘密情報を漏洩されたり不正利用されてしまうと、自社に多大な損害が生じる可能性があります。
そこで、相手方と「秘密保持契約」を締結することで、秘密情報の漏洩や不正利用を防止したり、相手方に起因して自社に損害が発生した場合の賠償の範囲をあらかじめ取り決めておくことができます。
また、「社員が増えたため、オフィスを借りたい」場合に、賃貸物件を借りる場合には、その物件のオーナーとの間で「賃貸借契約書」を締結することで、 物件の状態や入居中のルールなどを事前に確認し、入居後や退去時のトラブルを回避できます。
自社が目指す契約の目的(効果や価値)を明確にしておくことで、自社が目指す契約の目的を阻害するような契約内容を炙り出せます。
契約期間や契約金額を確認する
取引に必要な契約期間や契約金額なのかを確認することも重要です。
「自社が受注した開発の一部を外注したい」場合は、システムの開発に関する契約であれば、 開発に必要な期間が確保されているか、自社の支払金額や支払時期がいつかを把握します。
STEP2.リスクを抽出する
契約内容を把握することができたら、契約内容の中に自社にとって問題となる箇所がないか、リスクを抽出していきます。
- 目的物と対価は適切かを検討する
- 必要な条項は網羅されているか、不要な条項がないかを確認する
- 自社に不利な条項はないかを確認する
目的物と対価は適切かを検討する
目的物と対価は適切かを検討しましょう。
目的物とは、例えばシステムの開発に関する契約であれば、その開発業務により生じるシステムおよびそれに付随する成果物のことです。 契約書でその仕様を明確に特定しておく必要があります。
対価は、月額費用なのか単価なのか、支払期限や方法が自社の想定と合致しているかなどを確認する必要があります。
契約内容が曖昧に記載されていると、契約当事者双方が自社に都合の良いように解釈してしまい、後々のトラブルの引き金となります。
特に、取引における目的物や対価が曖昧な表現となっていると、双方が想定していた契約により得られる目的物や対価とズレが生じ、紛争につながるおそれが出てきます。
必要な条項は網羅されているか、不要な条項がないかを確認する
次に、取引において規定しておくべき必要な条項が網羅されているか、または規定しない方がよい不必要な条項がないか、 違法・無効な条件が含まれていないか、を細かく確認していきます。
取引の内容によって契約書に明記すべき項目が異なってきますので、その取引に適切な契約内容となっているかを慎重に確認する必要があります。
ここでは、その取引に適用される法令を調査したり、過去の類似契約や自社のひな形と比較するなどのリサーチをする必要があります。
例えば、システム開発業務を外部に委託する場合、委託側と受託側に一定以上の資本金規模の差がある場合は、 下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。すると、対価の支払時期など、 書面で明示しておかなければならない事項があるため、それらの事項が明確に記載されているかについて、十分に確認する必要があります。
自社に不利な条項はないかを確認する
そして、リスクの抽出においては、契約内容に自社が重い責任を負う内容が含まれていないか、 自社のビジネス上の制約となる条項がないか、など自社に不利な条項がないかを確認することも重要です。
例えば、自社が開発した成果物や開発業務に関連して生じた知的財産権について、全て相手方に帰属する内容の条項になっていた場合、 その開発業務に着手する前から自社が保有していた知的財産権のうち、その開発業務により生じた成果物に関連するものについても、 その後の自社の開発に自由に利用できなくなってしまう可能性があります。
また、自社にのみ一方的に義務が課せられている条項や、相手方にのみ有利な内容となっている条項も、 自社にとって不利な条項となりますので、全てリスクとして把握する必要があります。
関連記事
STEP3.修正案を作成する
契約内容およびその契約に潜むリスクが全て把握できたら、修正案の検討に入ります。
- 誤字脱字を修正する
- 不明確な箇所を修正する
- 自社にとって不利な条項を修正する
主に上記3つの観点で確認して修正を実施します。
誤字脱字を修正する
誤字脱字については、「てにをは」一字で文章の意味が変わってくる場合もあり得るため、全文を通して抜け漏れがないようにチェックをしていきます。
特に「甲」「乙」などの当事者が逆になってしまっている場合もよく見られるため、注意が必要です。
不明確な箇所を修正する
条件や範囲などが不明確な表現となっている箇所は、明確な表現に修正します。
曖昧な箇所を明確化することで、双方の認識の不一致をなくしていくことが重要です。
自社にとって不利な条項を修正する
自社にのみ一方的に義務が課せられている条項や、相手方にのみ有利な内容となっている条項は、 自社にとって不利な内容となっている箇所を削除したり、片務的な条項を双務的な条項に修正したりしていきます。
修正の際には、過去の類似契約や自社のひな形から参考となる条文案を探しましょう。
STEP4.修正案を確認する
修正案を作成したら、最終的な確認を行っていきます。
- フロント部門との認識のすり合わる
- 分かりやすく修正されているかを見直す
フロント部門との認識をすり合わせる
法務部門では判断できないビジネス観点での意見や、契約に至った背景、相手方との関係性などをヒアリングし、 修正案が現実的な内容となっているかを現場の担当者と認識を合わせていきます。
契約は今後の相手方との関係性にも大きく影響するため、自社の利益だけでなく相手方にとっても受け入れやすい内容とする必要があります。
分かりやすく修正されているかを見直す
最後に、相手方が理解しやすい修正となっているか見直します。全体を通しての判読性にも十分注意しましょう。
場合によっては、修正の意図や要望を、コメント機能などを利用して相手方へ伝えることも有用です。
関連記事
契約書レビューをするときに知っておきたいWordの使い方・機能10個
法務をシームレスに支援する次世代リーガルテック「LegalOn Cloud」
AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」は、法務業務をシームレスに支援する次世代リーガルテックです。契約審査から締結後の契約管理、法務相談案件の管理、法令リサーチ、法改正対応まで、あらゆる法務業務を最先端のAIを搭載したLegalOn Cloudがカバーします。日々の業務の中で生まれる自社の法務ナレッジ。LegalOn Cloudなら自然に集約、AIが自動で整理し適切なタイミングでレコメンド。ナレッジマネジメントの未来の形を実現します。
まとめ:契約書レビュー業務のやり方
契約書レビュー業務のやり方・流れは下記です。
- 契約内容を把握する
- リスクを抽出する
- 修正案を作成する
- 修正案を確認する
契約書レビュー業務を怠ると、契約書に不備があって、思わぬトラブルに発展する可能性があるため、契約書業務の中でも最も重要な工程といっても過言ではありません。
そのため本記事で解説したような手順で、専門家やシステムの力を借りながら、不備のない契約書を作成することが重要です。
<この記事を書いた人>
Nobisiro編集部
AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供するLegalOn Technologiesが運営する、法務の可能性を広げるメディア「Nobisiro」編集部。の法務担当者の日々の業務に役立つ情報を発信しています。