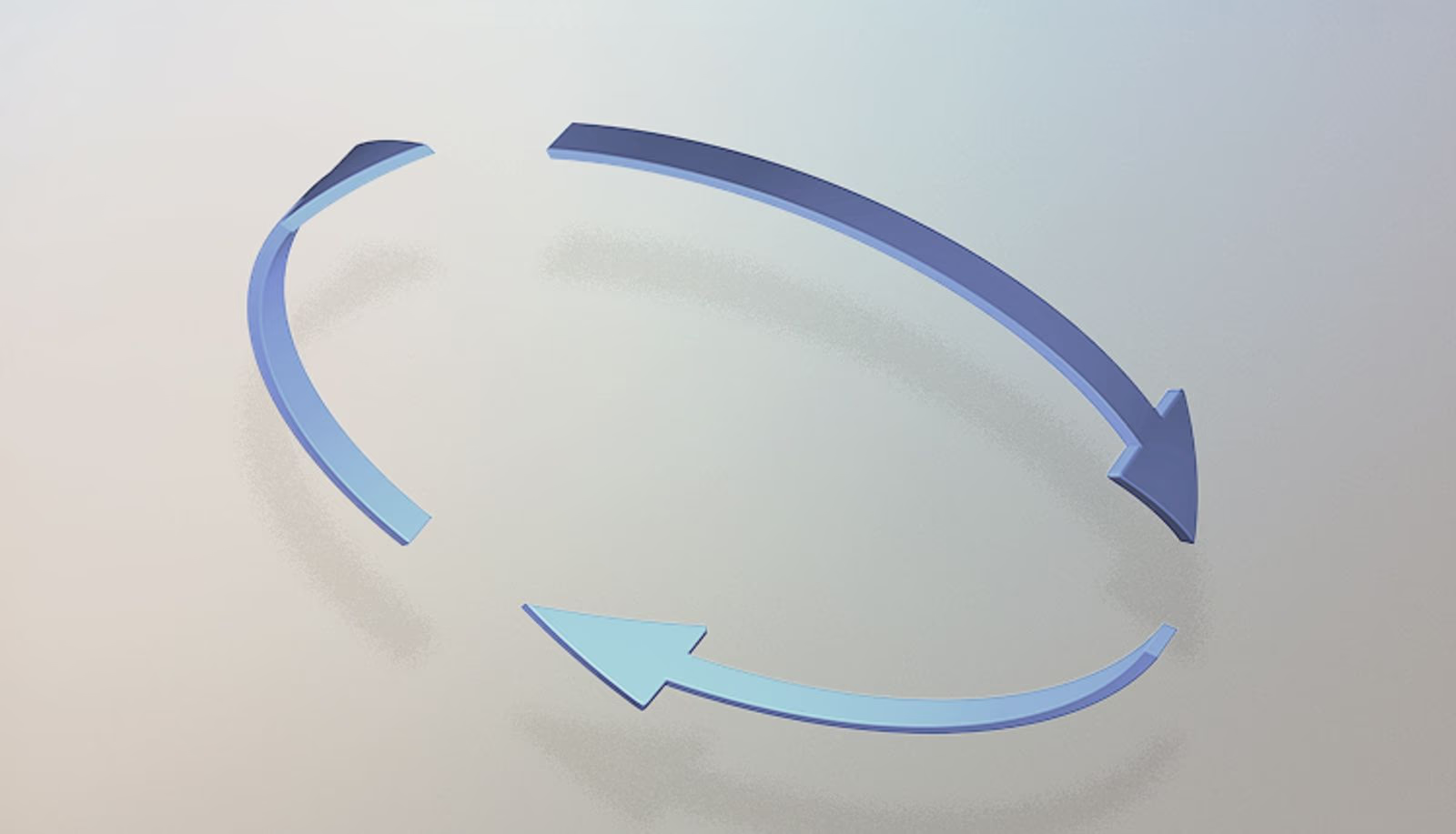CLM(契約ライフサイクルマネジメント)とは?
契約ライフサイクルマネジメント(CLM=Contract Lifecycle Management)とは、契約の締結前から締結後の管理・更新業務に至るまでのフローを管理し、最適化することをいいます。
契約業務には、さまざまな工程があります。契約書の受付から始まり、契約書ドラフトの作成や修正、契約書の締結、締結後の管理・更新業務に加え、内部承認のプロセスも必要です。
これらの一連の業務フローが適切に運用されなければ、業務効率が悪くなり、ビジネスのスピード感を損なうことにもなりかねません。また、あるべき工程の抜けが発生しやすくなるなど、業務の質にも支障が出てしまいます。
そこでCLMの手法や考え方を導入し、契約業務のフローを最適化することが重要です。特に、CLMを実現するITシステムの活用が注目されています。
CLMの必要性
ここではCLM(契約ライフサイクルマネジメント)の必要性についてご紹介します。
CLMは、契約フローの正常化やデータ管理の正常化によりリスク低減を実現します。契約の作成から更新、管理までを一元化し、関係者間のコミュニケーションを改善。これにより、迅速な意思決定とビジネスの透明性が向上し、企業の競争力を高めることが可能になります。
契約フローの正常化
契約プロセスの正常化は、企業運営において不可欠です。CLMを導入することで、契約の作成から承認、管理、更新に至るまでの一連のフローがスムーズになります。これにより、契約関連のミスを減少させ、ビジネスの迅速な展開を支援します。
また、関係者間の明確なコミュニケーションを促進し、契約プロセスの透明性を高めることができます。
正確で効率的な契約フローは、企業のリスク管理を強化し、最終的には企業の信頼性と市場での競争力を向上させることに繋がります。
データ管理の正常化
契約に関するデータ管理の正常化は、企業の情報整理とアクセス性の向上に寄与します。CLMを活用することで、契約関連のドキュメントやデータを一元化し、必要な情報を迅速に検索・参照することが可能になります。これにより、契約の状態や期限、更新履歴などを正確に把握し、適切な契約管理と運用が実現します。
また、データの一元管理はセキュリティの強化にも繋がり、不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減します。効果的なデータ管理は、企業の運営効率を高め、長期的なビジネス戦略の策定にも貢献します。
契約内容におけるリスク管理
契約ライフサイクルマネジメント(CLM)は、契約プロセス全体を通じてリスクを管理し、ビジネスの透明性と効率性を高めるために不可欠です。
契約書の作成から締結、更新、終了に至るまでの各段階で、多くの利害関係者が関与し、複雑なフローが生じます。この複雑さは、ミスや遅延、さらには法的な問題を引き起こすリスクを増加させます。
CLMを導入することで、これらのプロセスが一元化され、各ステップでの進捗が明確になり、リスクを効果的に管理できるようになります。結果として、企業は契約関連のミスを減少させ、ビジネスの遅延を防ぎ、全体的な運営の効率を向上させることが可能です。
契約内容の透明化・可視化
従来、契約関連の情報は散在しており、必要な情報を探すのに時間がかかることが多くありました。しかし、CLMを利用することで、契約書のドラフト、修正履歴、関連するコミュニケーションなど、すべての関連情報が一箇所に集約されます。これにより、関係者は必要な情報に迅速にアクセスでき、契約の状況をリアルタイムで把握することが可能になります。
また、契約プロセスの透明性が高まることで、内部のコミュニケーションが改善され、契約に関する共通の理解が促進されます。これらは、企業全体の契約管理の質を向上させ、最終的にはビジネスの成果に直結します。
リーガルコンプライアンスをサポート
契約ライフサイクルマネジメント(CLM)は、法的要件や規制遵守を強化する上で不可欠です。
企業が成長し、取引が国際化するにつれ、法的な複雑性は増大します。CLMを導入することで、企業は法的リスクを最小限に抑え、規制遵守を確実にすることができます。これにより、契約違反や訴訟のリスクが減少し、企業の信頼性と市場での競争力が向上します。
契約内容の精度と正確性を高める
CLMは、契約内容の精度と正確性を向上させることにも寄与します。契約プロセス全体を一元管理することで、誤解や曖昧さを排除し、契約書の一貫性と品質を保証します。
また、CLMシステムは、契約書のテンプレートを提供し、誤字脱字や不適切な条項の挿入を防ぎます。これにより、契約書の作成から承認、実行に至るまでのプロセスがスムーズになり、時間とコストの節約につながります。
正確で透明性の高い契約プロセスは、取引関係の改善とビジネスの効率化を促進します。
CLM(契約ライフサイクルマネジメント)の目的
ここではCLM(契約ライフサイクルマネジメント)の目的についてご紹介します。
CLMは、契約関連の業務を効率化し、企業の生産性を向上させることを目的としています。契約の発生から終了までの各ステージを明確に管理し、業務プロセスを標準化することで、時間とコストの削減を実現します。また、部門間のコミュニケーションを改善し、契約状況をリアルタイムで把握することが可能になります。
リスク防止
CLMを導入することで、契約遅延や更新漏れなどのリスクを未然に防ぐことができます。契約の各ステージを透明に管理し、契約の更新や終了に関するリマインダー機能を利用することで、重要な契約を見逃すことなく、適切なタイミングで対応することが可能です。
契約承認までのスピード化
CLMツールを活用することで、契約承認プロセスの迅速化が図れます。ワークフローの自動化により、契約書の作成から承認までの時間を大幅に短縮し、ビジネスのスピードを加速させることができます。また、電子契約システムとの連携により、紙ベースの契約プロセスから脱却し、より迅速かつ効率的な契約締結を実現します。
コミュニケーションコストをなくす
CLMの導入は、企業内のコミュニケーションコストを削減します。契約関連の情報が一元化され、関係者間での情報共有が容易になるため、誤解や情報の齟齬が減少します。
また、契約プロセスが明確になることで、必要な情報や文書を迅速に見つけ出し、効率的な意思決定を支援します。これにより、企業内のスムーズなコミュニケーションが促進され、業務の迅速化が図れます。
契約情報の検索性を高める
CLMシステムを利用することで、契約情報の検索性が大幅に向上します。過去の契約書や関連文書を簡単に検索できるようになるため、新たな契約書作成時の参考資料として迅速にアクセス可能です。
これにより、契約書作成の効率が上がり、業務プロセスが加速します。また、契約の履歴や詳細を瞬時に確認できるため、契約管理の正確性と透明性が向上します。
CLMを導入するメリット
CLM導入により、契約プロセスが効率化され、リスクが低減します。契約作成から管理、更新までを一元化し、自動化することで、手作業によるミスを減らし、時間を節約。リアルタイムで契約状況を把握し、更新漏れを防ぎます。これにより、企業は契約業務のスピードと正確性を向上させることができます。
契約管理の一元化
CLM(契約ライフサイクルマネジメント)を導入することで、契約管理が一元化され、ビジネスプロセスが大幅に効率化されます。
従来、紙ベースで行われていた契約書の管理は、紛失や誤送付などのリスクを伴い、また、必要な契約書を探すのに時間がかかるなどの問題がありました。しかし、CLMを利用することで、契約書の作成から保管、アクセス、更新までの全プロセスをデジタル化し、システム上で一元管理することが可能になります。
これにより、契約書の紛失リスクが減少し、必要な情報に迅速にアクセスできるようになります。さらに、契約のステータスをリアルタイムで把握できるため、ビジネスの透明性が向上します。
ビジネスの円滑化
CLMの導入は、ビジネスプロセスのスムーズな運営を支援します。契約プロセスの自動化により、契約書の作成から署名、保管に至るまでの時間が大幅に短縮され、ビジネスの迅速化を図ることができます。
特に、繰り返し発生する標準契約の場合、テンプレートを用いた契約書の自動生成や、電子署名による即時の契約締結が可能となり、ビジネスチャンスを逃すリスクを減少させます。
さらに、契約プロセスの透明性が向上することで、関係各所とのコミュニケーションが円滑になり、契約に関する誤解やトラブルのリスクを低減できます。
承認プロセスのスピードアップ
CLM(契約ライフサイクルマネジメント)を導入することで、企業は契約承認プロセスを大幅に加速させることができます。従来、紙ベースや手動のプロセスに依存していた契約作成から承認までの流れが、CLMによりデジタル化され、自動化されます。これにより、契約の作成、レビュー、承認が迅速に行えるようになり、ビジネスのスピードが格段に向上します。
さらに、契約関連のタスクにかかる時間が短縮されることで、営業チームや法務チームはより戦略的な活動に集中できるようになります。
過去の契約内容をすぐに確認できる
CLMシステムを利用することで、過去に締結した契約書を瞬時に検索し、確認することが可能になります。これは、契約書の保管と管理をデジタル化し、一元化することにより実現されます。結果として、必要な情報を迅速に取得できるため、意思決定におけるプロセスがスムーズになり、ビジネスの効率が向上します。
また、過去の契約内容を容易に参照できることで、リスク管理や契約更新時の交渉においても有利な立場を確保できます。
セキュリティ設定が適切に行える
CLMを導入することで、契約書のセキュリティ管理が強化されます。デジタル化された契約管理システムでは、アクセス権を細かく設定できるため、機密性の高い契約書へのアクセスを厳格に制御できます。
また、契約書の改ざん防止や、不正アクセスからの保護も強化されるため、企業の重要な情報資産を守ることができます。セキュリティの向上は、企業の信頼性とブランド価値の向上にも直結します。
CLMを構成する契約業務のフロー
CLMを導入するには、まず契約ライフサイクルを構成する各工程を細分化することが必要です。契約業務は通常、以下のような工程で構成されます。

- 契約の発生・契約審査受付
- 審査
- 交渉・修正
- 稟議・締結
- 管理
- 更新
それぞれの工程について、以下に解説します。
契約の発生・契約審査の受付
契約ライフサイクルのスタートは、相手方との取引内容を書面にした契約書を作成することです。発生する取引に適した自社のひな形が既にある場合、当該ひな形を相手方に提示します。適切なひな形がない場合、自社のひな形や過去に締結した契約書などを参考にしながら、法務担当者が契約書のドラフトを作成します。契約書のドラフトは取引先が作成する場合もありますが、ここでは自社で作成するケースで見ていきましょう。
作成した契約書のドラフトは、上司や担当部署に共有し、内容に問題がないか確認してもらう工程が必要です。
契約審査をする際は、担当部署と法務部で適宜ミーティングを行い、取引の種類(売買、業務委託、請負など)、成果物の有無、知的財産権の権利帰属、支払い条件、契約期間など、チェックに必要な情報を確認しましょう。
契約審査
相手方から契約内容について修正依頼があった場合は、法務部が契約審査を実施し、契約内容に問題がないかを確認します。
例えば、自社に不当なリスクのある条文が含まれていないか、必須とされる条文が抜けていないかなどの問題をチェックする工程です。誤字・脱字・表現の適切性・契約名義に誤りがないかなど、形式面も審査の際にしっかり確認します。
チェックの結果、必要に応じた加筆・修正案を提示することも法務部の役割です。
契約交渉・修正
契約審査で見つかった問題のある条文の変更などについて、相手方との交渉が必要になる場合があります。
こちらの提示する交渉内容に対して、相手方からさらに修正案が提示されることもあるでしょう。相手方からの修正案が出た場合は再度、法務部によるチェックを行います。
こうして最終版ができるまで修正と確認を繰り返します。
最終版が完成しても、途中のバージョンを削除せず残しておくことが一般的です。次の契約書を作成する際に、過去の契約書作成の途中過程を確認することがあるためです。
契約稟議・締結
最終版ができたら、稟議申請をします。承認が下りたら、契約書を締結する段階です。
紙の契約書で締結する場合
自社で契約書を印刷・製本する場合、通常2通作成し、押印をして相手方に郵送します。そして契約書を受け取った相手方に押印・日付の記入などの処理をしてもらい、2通のうち1通を返送してもらうという流れです。
相手方から押印済みの契約書が郵送されてくる場合もあります。どちらが契約書を印刷・製本するのか決まりはありませんので、最終版が確定した時点で、相手方に確認するようにしましょう。
電子契約で締結する場合
電子契約の場合は、郵送ではなく電子契約サービスを利用して契約書のPDFデータを電子的に送信します。それを受け取った相手方に、電子契約サービス上で締結処理をしてもらうことで契約書の締結となります。
契約書の管理・更新
締結した契約書を保存して適切に管理することも、CLMにおける重要な工程です。
紙の契約書なら、インデックスなどを付けた上でファイリングし、後から探しやすい状態で保管します。契約書名、取引会社名、担当部署、契約締結日、契約の更新日・有効期限などの情報や管理番号などを一覧化した「管理台帳」を作成しておくことも必要です。
契約期間が決まっている契約(自動更新なし)について、契約の更新期限が近づいてきたら、担当部署に連絡をして更新の有無を確認します。更新をする場合、契約更新についての覚書を作成するなどして契約を締結します。
また、自動更新ありの契約を放置して、不必要な契約が更新されてしまうことがないように管理することも重要です。担当者が常に更新日を把握できるよう、情報共有の体制を整える必要があります。
契約業務でおきがちな課題
契約業務ではさまざまな課題が発生しがちです。しかしCLMを適切に行うことで、多くの課題を解決できます。まずはどのような課題があるのか、代表的なものを見ていきましょう。
契約審査における課題
まずは契約審査の工程で発生しがちな課題についてです。主な課題として以下の2点が挙げられます。
- 契約書の作成・審査に時間がかかる
- 案件ごとのステータスを可視化できない
それぞれどのような課題なのか、以下より詳しく解説します。
契約書の作成・審査に時間がかかる
契約審査のために、確認作業や法律の調査などに「時間がかかる」という課題があります。
契約書を作成する際は、過去に作成した類似の契約書や、自社のひな形を利用できると効率的です。しかし、契約書をうまく管理できていないと、参照したい過去の契約書やひな形を見つけるのにも時間がかかってしまう場合があります。
過去の契約書やひな形の管理体制を整備することで、これらの作業を効率化することが可能です。
案件ごとのステータスを可視化できない
案件ごとに「審査中」「交渉中」などのステータスを把握できないという課題も発生することがあります。ステータスを把握できない状態では、進捗の遅れをケアできないなど、さまざまな問題が発生しがちです。
ステータスを把握できる一覧を作成するなど、社内に存在する契約案件を俯瞰的に管理できる体制をつくることが重要です。
契約管理における課題
契約書を締結した後にも管理上の課題はあります。主な課題として挙げられるのは、以下の3つです。
- 契約書の一元管理ができない
- 契約更新日を把握しづらい
- 閲覧権限の設定・セキュリティ管理ができない
契約書の一元管理ができない
どのように契約書を「一元管理」するかは、代表的な課題の一つです。
ここでいう一元管理とは、契約書の検索や内容の閲覧など、契約管理に必要な作業を一つのシステム上で完結できるような状態を指します。
例えば契約書の情報を一覧化した「管理台帳」をエクセルで作成するだけでは、一元管理とまではいきません。この場合、契約書の詳しい内容を確認するには、台帳で契約書の保管場所を調べ、キャビネットを開けてファイルを探すなどの手間がかかります。
一元管理を実現するには、契約書の一覧から簡単な操作で契約書の内容まで閲覧できるような仕組みを実現することが必要です。
「LegalForceキャビネ」を導入すれば、契約書の検索と閲覧までシステム上で完結できます。さらに契約書のPDFデータを読み取って、管理台帳に反映させる機能があり、契約書情報の一覧を効率的に作成できます。
契約更新日を把握しづらい
「契約更新日を把握しづらい状態」で契約書を管理してしまっている場合にも課題があります。
契約の更新日を把握しづらい状態で契約書を管理していると、契約更新手続きが必要な契約を更新し忘れてしまったり、不要な自動更新契約を放置することによって本来なら解除すべき契約が更新され続けてしまう、といった損失が発生することになりかねません。
この点でも「LegalForceキャビネ」を導入することで、効率的な仕組みをつくることができます。契約書の更新日を自動的に知らせるリマインド機能によって、不要な契約の更新や、重要な契約の終了を防止することが可能です。
閲覧権限の設定・セキュリティ管理ができない
契約書を閲覧できる人を制限するなど、「セキュリティ対策」をどうするかも重要な課題です。
例えば紙の契約書なら、契約書原本を保管するキャビネットに施錠するだけでなく、閲覧・持ち出しルールを整備する必要があります。しかし関係するスタッフ全員にルールを徹底してもらうことが難しい場合もあり、十分な対策ができないと感じるケースもあるでしょう。
スキャンしてPDF化した契約書についても、セキュリティ対策に課題はあります。例えば、契約書のデータを保存しているファイルサーバにパスワードを設定するなど、セキュリティ対策のために多くの手間がかかってしまうことがあります。
LegalForceと連携できる契約書の管理システム「LegalForceキャビネ」では、必要なセキュリティ対策を効率的に設定することが可能です。権限管理の機能があり、閲覧できるユーザーの制限を一括設定できます。
AI契約書レビューは次のステージへ
CLMを確実に実行するには、契約法務の一連の業務を一貫して管理することが重要です。その際にどのような課題があり、突破するにはどのような取り組みが重要か、資料を無料で公開しています。
契約の基本についてさらに詳しく知りたい方は、以下のダウンロード資料もご利用ください。
「契約とはどのようなもので、なぜ契約書を作成する必要があるのか」等、契約に関する基礎理解を深めたい方におすすめの資料を無料で配布しています。
<この記事を書いた人>
Nobisiro編集部
AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供するLegalOn Technologiesが運営する、法務の可能性を広げるメディア「Nobisiro」編集部。の法務担当者の日々の業務に役立つ情報を発信しています。