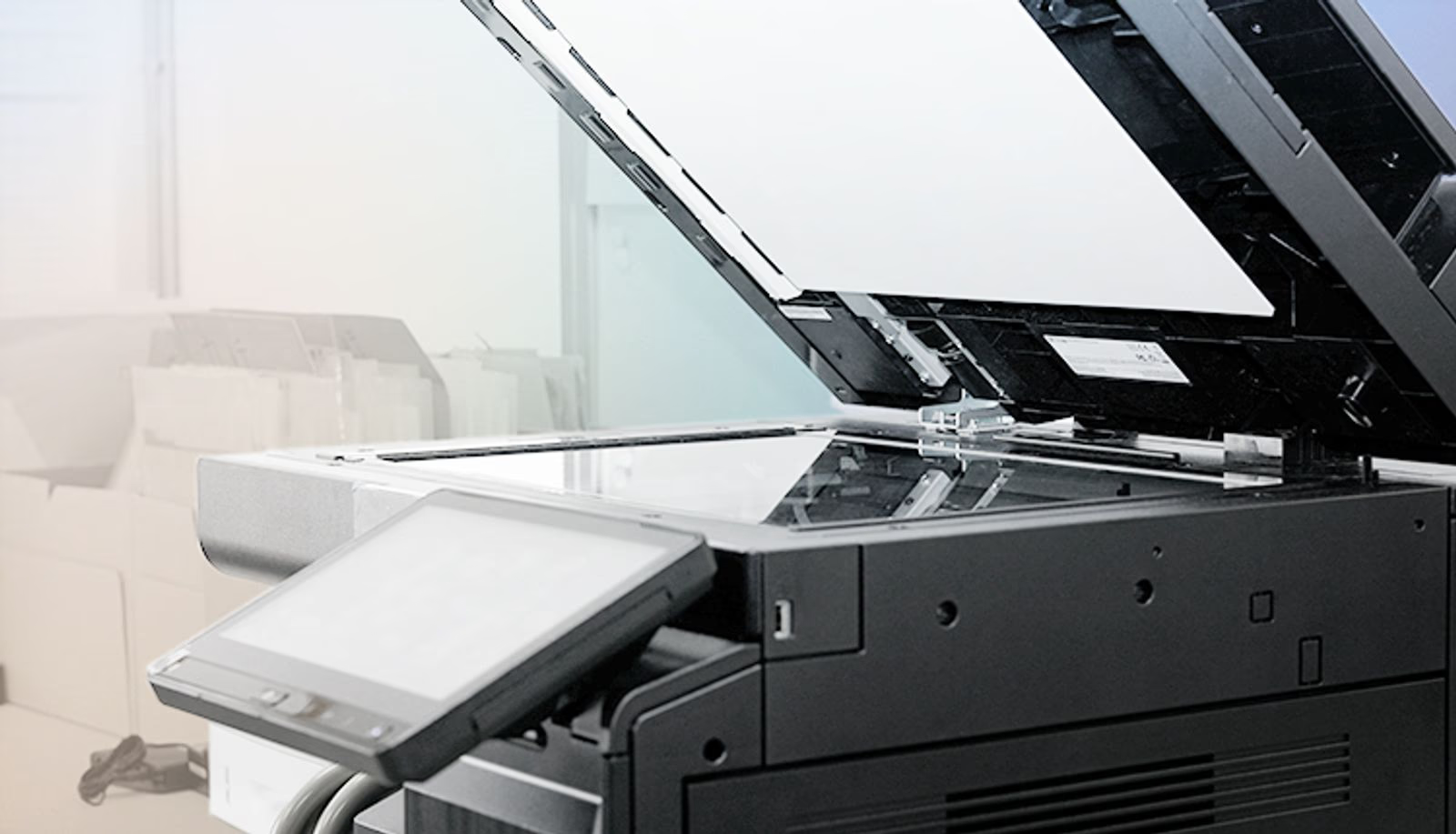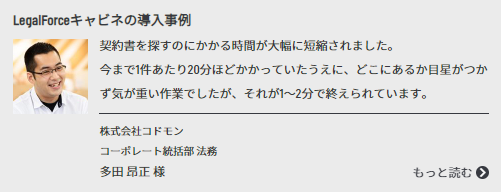契約書はPDFスキャンして保存してもよいのか
「契約書のスキャン」とは、紙の契約書をスキャナで読み取り、PDFなどの電子データとして保存することです。一定の条件を満たしていれば、スキャンした契約書でも証拠としての効力が認められます。
根拠となる法律は2つ。税務上の文書としての効力を定める「電子帳簿保存法」と、民事訴訟における書証(文書による証拠)の効力を定める「民事訴訟法」です。
ただし2つの法律では、スキャン保存した契約書の取り扱いに違いがある点に注意が必要です。
電子帳簿保存法では、スキャン保存した契約書を「国税関係書類」の原本と認めています。(電子帳簿保存法第2条第2号、第4条第3号)
民事訴訟法ではスキャンをした契約書は、文書の「原本」としては取り扱われません。しかし「準文書」として、データが裁判官の証拠調べの対象となる証拠となります。(民事訴訟法231条)
このように電子帳簿保存法・民事訴訟法ともに、契約書をスキャンしたデータについて、一定の法的効力があることを認めているのです。
<関連記事>
契約書を電子化するメリットとは?電子契約の導入方法や注意点を解説
Word契約書のPDF化も可能
紙の契約書をスキャンするだけでなく、Wordで保存されている契約書もPDF化することも可能です。手順は、下記のとおりです。
- PDFに変換したいWordファイルを開く
- メニューバーの「ファイル」をクリックし、表示されるドロップダウンメニューから「保存または名前をつけて保存」を選択
- 「保存または名前をつけて保存」の下部にある「形式」または「ファイルの種類」で「PDF」を選択
- 任意のファイル名と保存場所を指定し、「保存」を選択
以上の手順で、WordファイルはPDFに変換され、指定した場所に保存されます。この手順はMicrosoft Wordの基本的な機能を使用しているため、特別なソフトウェアを追加でインストールする必要はありません。
<関連記事>
契約書レビューをするときに知っておきたいWordの使い方・機能10個を解説!
契約書をスキャン保存するメリット
契約書をスキャン保存すると、具体的には以下のとおり2つのメリットがあります。
閲覧・共有がしやすくなる
スキャン保存により電子化した契約書は、その閲覧と共有が容易になります。
紙の契約書を閲覧するには保管場所へ実際に足を運ぶ必要があり、複数名で一つの契約書を共有することは困難です。
この点、スキャンした契約書なら、ネットワークを使ってリモートでも閲覧できます。複数メンバーで同時に一つの契約書にアクセスして共有することも可能です。
契約書の閲覧と共有がしやすくなることで、契約書業務の効率化が実現できます。
管理・保管がしやすくなる
契約書の管理・保管が効率化できることも、契約書をスキャン保存するメリットです。
契約書をスキャンした後に原本を破棄できる場合には、その保管スペースが不要になります。
また紙の契約書の場合、火事など災害による消失や、時間経過による劣化などのリスクもありますが、電子データなら複数の場所にバックアップを取りやすく、その点のリスク対策が容易です。
さらに契約書の保管においてはセキュリティ対策が重要ですが、この点でもメリットがあります。紙の契約書は、持ち出した際に紛失するなどのリスクがありますが、電子データなら契約書を外部に持ち出す必要がありません。契約書のデータにアクセスできるメンバーを制限することも容易で、セキュリティ面の管理がしやすくなります。
印紙代などコストの削減
契約書をスキャン保存すると、印紙代などのコストを削減できます。
紙の契約書では、プリントアウトや配送などに関連するコストが発生します。対して、電子契約では物理的な印刷や郵送は不要です。結果として、紙やインク、郵送費などの出費を大幅に削減できます。また、プロセスを簡単にすることで、人員の作業時間短縮も実現されます。
さらに、紙ベースの契約書は印紙税が課される対象でしたが、電子契約はこの税制の対象外であるため、ここでもコストを削減できます。これらの節約は一契約あたりでは少額かもしれませんが、これが大量の契約に積み重なると、企業にとっては大きな経費削減となります。
テレワークに対応できる
テレワークという現代の働き方に対する対応という観点から見ても、契約書のスキャン保存は大きなメリットです。
従来の紙ベースの契約書では、オフィス外での契約手続きの完結や契約書の内容の確認が難しいという問題がありました。契約書の印刷や印鑑の押印、さらに郵送の準備など、これらの一連の作業はオフィスの設備とリソースを必要とします。
しかし、電子契約書をPDF形式で利用することで、これらの課題解決が可能です。PC、タブレット、スマートフォンなどのデバイスを使って、場所を選ばずに契約書を管理することによって、テレワーク環境でも作業効率が上がります。どこからでも容易に内容を確認できつ点は、リモートワークが一般化する現在の労働環境において大きなメリットと言えるでしょう。
ガバナンスの強化
ガバナンスの強化が図れる点も、契約書をスキャン保存するメリットです。
契約書には機密情報が含まれることもあるため、情報が第三者によって覗かれたり、持ち出されたり、紛失あるいは破損したりするリスクを防止する必要があります。この観点から、PDF形式の契約書は有用性を発揮します。
PDFでは、各ファイルに対してパスワードを設定することができ、情報への不正なアクセスを防止できます。また、物理的な紛失や破損のリスクもなくせます。さらに、電子署名やタイムスタンプの使用により、契約書の原本性の保証も可能です。
これにより、契約書をスキャン保存するとガバナンス強化が実現されます。今日のビジネス社会では、企業の健全な経営と法規制の遵守が重要視されています。契約書をPDF化すれば、不正防止や情報の透明性向上といった効果が期待できます。
関連記事
法的な効力のある契約書スキャンをするための要件
スキャンした契約書を、国税関係書類として扱うために満たすべき要件を「スキャン要件」と呼びます。スキャン要件の詳細は、国税庁により発表された以下のリンク先資料に掲載されています。
スキャン保存の要件のうち、ポイントとなるのは以下の3点です。
- タイムスタンプの付与
- 適切なスキャナの使用
- 検索機能の確保
この3点について、以下に詳しく解説します。
タイムスタンプの付与
タイムスタンプとは、PDFを含む文書ファイルに「文書の作成時刻」を記録する仕組みです。TSA(時刻認証局)という第三者機関と通信することで、公証された時刻の記録を文書に付与します。
ただし一定の条件を満たすことにより、タイムスタンプを省略できるように2022年の法改正で要件が緩和されました。具体的には、時刻証明機能を提供するクラウドシステムなどに保存し、時刻証明や、改ざんのないことを証明できれば、タイムスタンプの付与は不要です。
なお、時刻証明機能を他社へ提供しているベンダー企業以外は、「自社で開発したクラウドシステム」などによるタイムスタンプの代替はできないとされています。詳しくは、国税庁の作成した下記資料をご覧ください。
適切なスキャナの使用
契約書スキャン保存には、「適切なスキャナ」を使って行う必要があります。利用できるスキャナの規定は以下のとおりです。
・スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。
・赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること。
・一般書類(電子帳簿保存法施行規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類)をスキャナ保存する場合、白色から黒色までの階調が256階調以上で読み取るものであること。
引用元|Ⅰ通則【制度の概要等】問5「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか|国税庁
上記の規定は、現在の一般的なカラースキャナの多くで満たせるものです。また、国税庁からの取扱通達により、必ずしも「スキャナ」と呼ばれる機器である必要はなく、スマートフォンのカメラ・デジタルカメラなどでも代用が可能とされています。
検索機能の確保
スキャン保存の要件として、契約書を「検索できる機能」を備えておくことが必要です。
例えば、クラウド契約管理システムやエクセル上で検索可能にしておくことによって、要件を満たすことができます。
ただし、電子帳簿保存法施行規則の検索機能に関する規定により、検索機能は次のような設定ができるものでなければならないとされます。
・取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること
・日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
・二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
引用元|電子帳簿保存時の要件|要件5 検索機能の確保 施行規則第3条第1項第5号|国税庁
「帳簿」とありますが、契約書の場合も同様です。台帳などを使って、契約の締結日・契約終了日・更新日・金額・日付などを基準に契約書を整理し、これらの要素をシステムやエクセル上で指定して検索できるようにする必要があります。
契約書スキャンのデメリット・注意点
契約書のスキャン保存する際に陥りがちな問題・課題について、その対策を含めて解説します。
スキャン作業の手間がかかる
紙の契約書のスキャン作業には、時間がかかります。契約書の保管通数・作成通数が多い会社であればなおさらです。
スキャン作業そのものだけでなく、ステープラー・付箋はずし、スキャンした書類の片付けなど、スキャン前後の作業にも多くの手間と時間がかかります。
スキャン代行業者などにアウトソーシングして行う場合でも、作業指示の手間がかかり、スキャン前作業などは依頼する会社側で行うのが一般的です。
対策としては、作業に優先順位をつけることが挙げられます。例えば、電子帳簿保存法が改正された2022年1月1日以降に作成した契約書から優先的にスキャンするなどの対応です。また、ほとんど参照しない契約書はスキャン対象から外すといったこともできます。
より抜本的な対策は「電子契約」の導入によるペーパーレス化です。電子契約ならそもそも紙の契約書を作成しないので、スキャン作業は必要なくなります。
データの保管・管理の対応が必要
スキャンしたデータをどのように管理するかという点も課題です。検索などの必要な機能を確保しつつ、セキュリティ面にも気をつける必要があります。
スキャンしたデータをそのまま保存しただけでは、検索機能を持たせることはできません。そのためには契約内容を参照しながら台帳に必要な情報を入力するなどの作業が必要で、場合によっては膨大な手間がかかります。
また不正アクセスによる契約書データの漏洩などが発生しないよう、セキュリティ面の対策をどのように整えるかという課題にも取り組むことが必要です。
この点の対策としては、「自動スキャン機能」のあるシステムを利用するという方法があります。自動スキャン機能とは、スキャンしたPDFデータなどを自動で読み取り、必要なデータを抜き出して台帳に入力するという機能です。
契約管理システム「LegalForceキャビネ」なら自動スキャン機能だけでなく、セキュリティ面の対策がなされた状態で、スキャンした契約書を管理・保管できる機能があります。
<関連記事>
契約書管理はどの部署で行うべき?主な4つのパターンを解説
原本を破棄できるとは限らない
スキャン保存について、注意したいのは、中には原本を廃棄してはいけない契約書があるという点です。
電子帳簿保存法では、スキャン保存されたデータを原本と照らし合わせて確認する作業を要求する「適切処理要件」という規定が廃止されたため、紙の原本は廃棄可能とされています。
ところが、契約書の中には法律で必ず書面で作成することとされているものがあり、紙の原本を破棄できないことがあります。例えば「事業用定期不動産賃貸借契約書」などです。
また、過去の契約書も、法律で「保管年限」が決められているものがあります。例えば法人税法施行規則(第59条第1項第3号)では契約書の保存期間は7年であり、その期間中は廃棄できません。
訴訟での証拠力が弱くなるリスクがある
スキャンした契約書は「原本」として扱われないため、証拠力の点では弱くなる可能性がある点に注意が必要です。
民事訴訟規則に以下のような条文があります。
〇民事訴訟規則(文書の提出等の方法)
第143条 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
引用元|民事訴訟規則第143条|裁判所ウェブサイト
「原本、正本又は認証のある謄本」とあるため、コピー文書が認められない可能性があり、また2項を相手方の訴訟戦術に使われ、コピーの文書は「改ざんしたもの」として証拠力を否定されてしまう可能性が考えられます。
これらの理由から、訴訟に備えるためには紙の原本の保管も必須であり、スキャンした契約書では原本である紙契約書の代替はできないという見方が、専門家の間では一般的です。
この点の対策方法として、電子署名入りの「電子契約」の導入が挙げられます。電子契約データは原本と同等の証拠力を持つと考えられるためです。
編集時にはOCR処理が必要
スキャンした契約書のPDFファイルは、基本的に文字情報を自由に編集できません。PDF化した契約書内の情報をテキストデータとして活用するためには、OCR(光学的文字認識)という処理を行う必要があります。これは画像から文字情報を抽出する技術です。
しかし、編集をしたい際はOCR処理も完全な解決策とは言えません。OCR処理をすると、手書き文字やバーコード、特殊な形状の文字まで識別できますが、それでも完全な正確さを保証するものではありません。ある文字が他の似た文字に間違えられる可能性もあるため、その点はあらかじめ留意しておきましょう。精度を確保するためには、人間による目視確認が必要です。
原本として認められないケースがある
契約書をスキャンする際には、契約書が原本として認められなくなる点がある点に注意しましょう。
2022年の改正電子帳簿保存法では、特定の要件を満たせばスキャンした契約書でも、元の紙の契約書を破棄しても問題ありません。しかし、訴訟などの法的な問題が発生した場合は、PDFの契約書だと証明力が否定されてしまう可能性があります。
また、2021年12月31日までに作成された紙の契約書をスキャンして保存する場合、電子帳簿保存法に基づいて「適用届出書」を税務署長に提出する必要があります。この届出書には、保存する書類の詳細が記載されていなければなりません。ただし、2022年1月1日以降に作成または受け取った文書については、税務署長の事前承認は不要です。
契約書スキャンを効率的に進める方法・コツ
これまで見てきたように、契約書スキャン作業やその後の契約書管理には多くの手間がかかる点が課題です。
スキャン作業をできるだけ効率的に進めるために役立つ3つの対策を、以下に解説します。
契約書スキャン代行サービスを利用する
一つは契約書スキャン代行サービスを利用し、代行業者に依頼してスキャンするという方法です。
事前のスキャン準備作業や、代行業者に対する指示書を作成するなどの手間は発生することがありますが、工程の大きな割合を占めるスキャン作業自体には社内リソースを割く必要がなくなります。
契約管理システムを導入する
契約管理システムの導入もおすすめです。クラウド型の契約管理システムの多くには、スキャンデータの保存や、検索機能をサポートする機能が付いています。
契約管理システム「LegalForceキャビネ」には、台帳自動登録機能があり、手入力で台帳を作るのではなく、スキャンデータから自動で台帳作成を行うことができます。
電子契約を導入する
電子契約を導入し、紙での契約書を作成しないようにすると、スキャン作業自体の必要がなくなります。
電子契約とは、電子データによって契約を締結する方法です。紙の契約書を作成することなく、契約書内容が書かれたワードファイルなどをPDF化して、電子署名データを付したものを原本として扱います。
電子契約は電子署名によって改ざんしにくい状態で保存することができ、証拠力も高いとされています。また電子契約はオンラインで可能なので、押印のために会社や会議室などに出向く必要もありません。
LegalForceキャビネでは電子契約システムとの連携ができ、締結した電子契約データの保存・管理も可能で、契約書管理の効率化・一元化ができます。
PDFスキャン後の契約書管理は「LegalForceキャビネ」で
契約書をスキャンすることは、閲覧・共有のしやすさや、契約書の管理・保管の効率化など、多くのメリットがあります。
契約書のスキャンと、スキャンしたデータの管理を効率化するには、「LegalForceキャビネ」が有効です。スキャン要件を満たす「検索機能」があるほか、「台帳自動登録機能」を利用すれば、スキャンデータから検索用のデータを台帳へ自動入力できます。
電⼦契約サービスとの連携にも対応している点も「LegalForceキャビネ」の特徴です。電⼦契約であれば、締結した契約書をスキャンし直す必要がなく、そのままデータで管理できます。契約書を一々スキャンするのではなく、この機会にデータで一元管理したいと考えている経営者様やバックオフィスのご担当者様に「LegalForceキャビネ」はおすすめのシステムです。
LegalForceキャビネの機能の詳細については、以下のフォームより資料をご請求のうえご確認ください。
【法務担当の方へ】
法律上契約書は何年保管すればいいのか、知っていますか?
以下の無料資料をダウンロードして、契約書の保管期間と保管方法を網羅的に理解しましょう。
<この記事を書いた人>
Nobisiro編集部
AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供するLegalOn Technologiesが運営する、法務の可能性を広げるメディア「Nobisiro」編集部。の法務担当者の日々の業務に役立つ情報を発信しています。